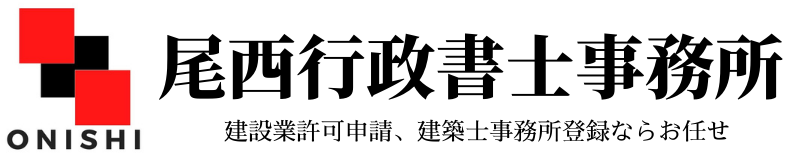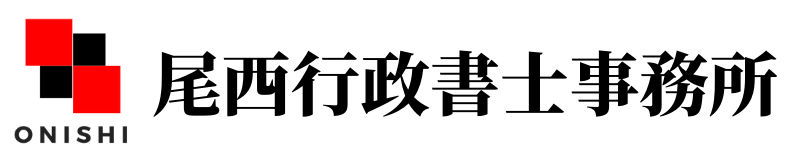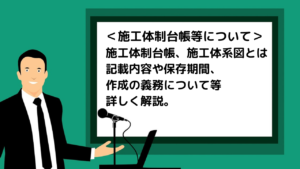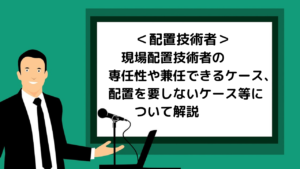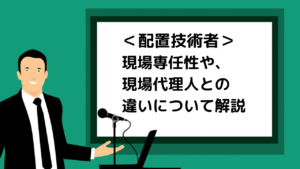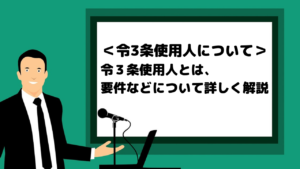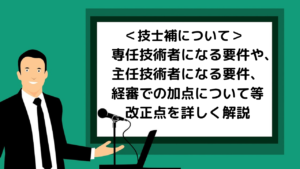工事の「JV」って、たまに聞くけど、何のことかしら?、尾西先生



今回は建設業におけるJVの定義や、種類、メリット、デメリットなどを詳しくわかりやすく、解説します
JVとは
建設業におけるJV(ジョイントベンチャー)は、「共同企業体」を意味し、複数の建設業者が共同で工事を請け負い、施工を行うための形態を指します。
JVは大規模で複雑な工事や、各企業の技術やリソースを組み合わせて効率的に工事を進める必要がある場合に活用されます。
ざっくりと言うと、大規模な建設工事を複数の企業で受注、施工する組織のことになります。(「事業組織体」という組合のようなもの)



JVは複数の建設業者による組合みたいなものなのね



JVにも、いろんな種類があります
JVの種類
JVには、まず①特定建設工事共同企業体(特定JV)と、②経常建設共同企業体(経常JV)の2つがあります。
2つのJVの違いは下記のようになっています。
●定義の違い
特定JV
特定の工事を遂行するために結成されるJV。特に公共工事などの一つのプロジェクトに対応するための期間限定の組織。
経営JV
複数のプロジェクトや長期的な事業活動を行うために結成されるJV。
●形態
特定JV
特定の工事の施工を目的として、工事ごとに結成し、工事完成後又は工事を受注できなかった場合は解散する。
経営JV
中小・中堅建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する。
●活動範囲
特定JV
一つの特定のプロジェクトにのみ活動を限定。プロジェクト終了後は解散。対象となる工事は、大規模で技術的難易度の高い工事。
経営JV
複数のプロジェクトや長期的な事業活動を目的とする。継続的な経営活動を行うことを想定している。
●主な目的
特定JV
公共工事など、単独で対応できない大規模工事や専門性の高い工事を遂行するために、複数企業が協力。
経営JV
新規事業開拓や市場拡大、リスク分散、または技術や資本の融合を目的とした長期的なビジネスパートナーシップ。
●利用される場面
特定JV
大規模公共工事(道路建設、ダム建設など)、技術が多様な工事、発注条件を満たすための協力体制が必要な場合。
経営JV
長期的な新規事業(例:エネルギー開発プロジェクト)、複数プロジェクトへの対応、市場拡大を目的とした事業提携。
また特定JV、経営JVの他にも③地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)、④復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)があります。
<地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)の特徴>
・地域内の建設業者が単独で対応できない小規模工事や継続的な業務の需要に応える
・地元業者間の連携強化、地域経済への貢献
・地域の小学校や役所の耐震補強工事、地域の橋や道路の補修業務などを行う
・地域の日常的なインフラ維持を目的とし、地元業者が中心となる小規模・中規模の活動が主体
<復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)の特徴>
・災害時に迅速かつ効率的に対応するため、大手と地元業者が協力
・災害発生直後の応急対応や、長期的な復興計画に基づく工事が含まれる
・震災後の道路や鉄道の復旧、津波被害を受けた堤防の再建
・復旧・復興JVは、災害時の迅速な対応が求められる復旧・復興工事を目的とする



JVにも、いろんな種類があるのね



工事の目的や場面によって、4つのJVが使いわけられています
JVの施工方式(甲型、乙型)について
JVの施工方式は、甲型JVと乙型JVの2つに分かれます。
甲型JVは、1つの工事について、各々があらかじめ定めた出資割合に応じて資金、人員、機械等を拠出して共同施工する施工方式です。
乙型JVは、1つの工事を複数の工区に分けて、各構成員はそれぞれが担当する工区の工事を施工する方式です。





へえ、施工方式にも違いがあるのね



甲型JVか、乙型JVかによって主任技術者、監理技術者の配置の仕方が異なってきます
JVの主任技術者、監理技術者について
JVの主任技術者、監理技術者の配置については、JVの施工方式(甲型または乙型)によって異なってきます。
甲型JVの場合で、下請代金の総額が4,500万円未満の場合は、全ての構成員が「主任技術者」を配置することになります。


甲型JVで下請代金の総額が4,500万円以上の場合、構成員のうち1社が監理技術者を配置し、ほかの構成員が主任技術者を配置することになります。


乙型JVの場合で、分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円未満の場合は、全ての構成員が「主任技術者」を配置することになります。


乙型JVの場合で、分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円以上の場合は、総額が4,500万円以上となった建設業者は「監理技術者」を、その他の建設業者は「主任技術者」を配置することになります。





JVの施工方式と下請代金の総額によって、主任技術者を置くか、監理技術者を置くかが変わってくるのね



配置技術者を間違えないように気をつけましょう
JVが必要とされるケースとは
ジョイントベンチャー(JV)が必要とされるケースは、複数の企業が協力することで個別の企業では対応しきれないプロジェクトや課題を解決する場合です。以下に具体的なケースを挙げます。
<大規模なプロジェクトへの対応>
JVは、単独の企業では対応が困難な大規模プロジェクトを遂行するために結成されることがあります。
事例: ダム建設、空港建設、長大な道路工事など。
理由: 資本、人材、設備を複数の企業で分担することで効率よくプロジェクトを進行できる。
<高度な技術や専門性が必要な場合>
異なる分野の専門知識や技術を持つ企業が協力してプロジェクトを遂行する際にJVが活用されます。
事例: 高層ビルの建設、原子力発電所の建設、複雑な機械設備工事。
理由: 各企業の強みを結集して、技術的な課題を克服する。
<公共工事における発注条件の充足>
公共工事では、特定の規模や実績を求められる場合があり、単独企業で条件を満たせない場合にJVが組まれます。
事例: 国や地方自治体が発注する大型公共工事。
理由: 発注者の要件を満たすために、複数の企業が連携する。
<災害復旧・復興のための緊急対応>
大規模災害後の迅速な復旧・復興を目的として結成されることがあります。
事例: 震災後の道路復旧、仮設住宅の建設、堤防再建。
理由: 大規模かつ迅速な対応を実現するために、リソースを集約する必要がある。
<地域維持や小規模工事への対応>
地域内のインフラ維持や管理を目的とした場合に、地元企業が結成するJVです。
事例: 道路の補修や橋の維持管理業務。
理由: 地域経済への貢献や、小規模工事への柔軟な対応を可能にする。
<リスク分散の必要性>
プロジェクトのリスクを複数企業で分散するためにJVが利用されます。
事例: 新技術を用いたプロジェクト、予算が大きいプロジェクト。
理由: 財務的リスクや技術的リスクを軽減する。
<市場参入や事業拡大>
新しい市場や分野に進出する際に、既存のプレイヤーとJVを結成することがあります。
事例: 新興国でのエネルギー事業、医療施設の建設。
理由: 地域の市場知識や人脈を活用できる。
<発注条件での特定要件>
公共事業などでは、発注者がJVでの対応を指定する場合があります。
事例: 入札要件としてJVの結成が求められる。
理由: 発注者がプロジェクトのスケールや複雑さを考慮し、複数企業の協力を前提にしている。
JVは、資源や能力を共有し、単独では実現困難なプロジェクトに対応するために組まれることが多いです。
その用途は幅広く、地域維持や小規模工事から国際的なインフラプロジェクトまで多岐にわたります。どのようなケースでJVが必要かは、プロジェクトの規模、特性、目的によって異なります。



じつにいろんな場面でJVが必要とされるのね



次の段落では、JVのメリット、デメリットを紹介していきます
JVのメリット、デメリット
JVのメリット、デメリットについて、特定建設工事共同企業体(特定JV)と、経常建設共同企業体(経常JV)、③地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)、④復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)の4つの種類ごとにメリット、デメリットを下記にまとめました。
<特定JVのメリット>
・一つのプロジェクトに集中して協力できる。
・リスクや責任を構成員間で分散可能。
・解散後に各企業は独立性を保てる。
<特定JVのデメリット>
・一時的な組織であり、長期的な計画には不向き。
・プロジェクト終了後、ノウハウの蓄積が難しい。
<経営JVのメリット>
・長期的な事業活動が可能。
・技術や資本を融合して市場競争力を高められる。
・単独企業では難しい大規模なビジネス展開が可能。
<経営JVのデメリット>
・継続的な運営に伴うコストがかかる。
・経営や利益分配で意見の相違が生じるリスクがある。
<地域維持型のJVメリット>
・地元業者が協力して工事を請け負うため、地域経済の活性化につながる。
・地域の特性やニーズに応じた柔軟な対応ができる。
・地元企業同士の連携がしやすく、迅速な意思決定や調整が可能。
<地域維持型JVのデメリット>
・地元の小規模業者が中心となるため、特定の技術や経験が不足している場合がある。
・地域の需要が少ない場合、JV全体の収益が悪化するリスクがある。
<復旧・復興JVのメリット>
・災害復旧では時間が最も重要な要素であり、複数企業が協力することで作業を早期に開始できる。
・災害現場特有の課題に対して柔軟な解決策を立案できる。
・災害復旧では予測不能なリスクが多いが、JVを通じてリスクを分散できる。
<復旧・復興JVのデメリット>
・緊急時には作業が優先されるため、後で問題が発生した場合に、責任の所在が不明確になるリスクがある。
・ノウハウの蓄積や次回の災害時への備えが難しい。



JVの種類によって、メリット、デメリットが異なってくるのね



その通りです
まとめ
〈まとめ〉
・現場配置技術者に専任性が求められる場合、元請業者の技術者は、原則、契約の工期期間中は専任が必要。ただし、一定の条件に該当する場合は、必ずしも専任設置を必要としない。
・専任を要する工事の契約工期が重複する場合でも、「専任を要しない期間」同士が重なる場合であれば、重複することは可能。
・公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
・2人の1級技士補を専任の技術者として、2つの工事現場に配置することで、監理技術者が1人で2つの工事現場を兼任することができる。
・一次下請及び二次下請は、合意により一次下請けが配置する主任技術者が、その行うべき技術上の施工管理と併せて、本来であれば二次下請の主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うこととしたときは、二次下請は主任技術者を配置することを要しないこととすることができます。



当事務所では建設業許可の申請を承っております