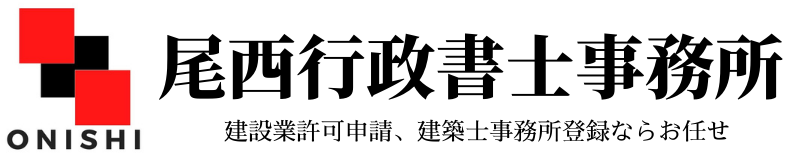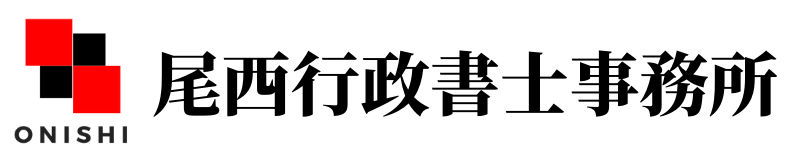-

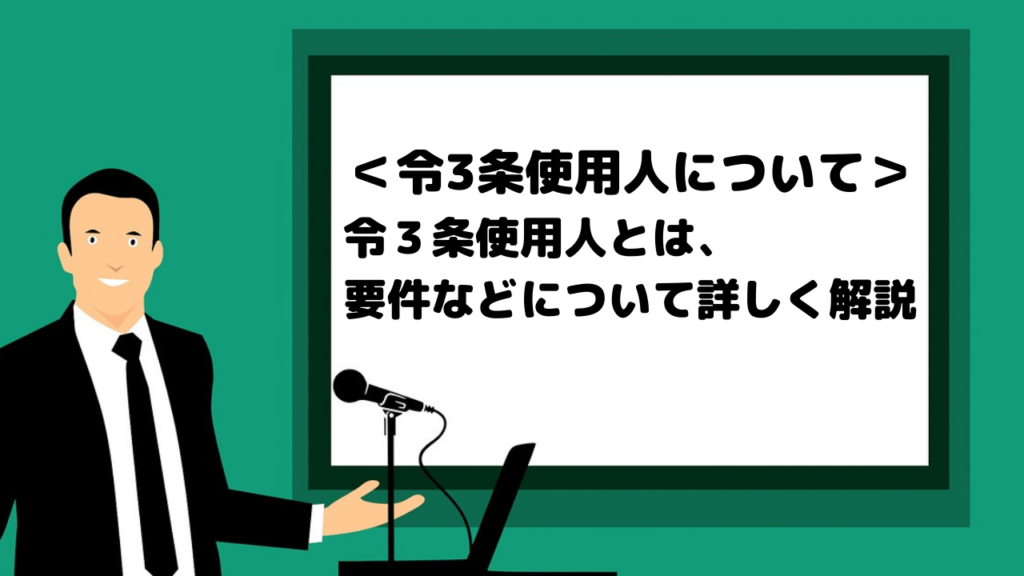
令3条使用人とは、要件などについて詳しく解説
尾西先生、「令3条使用人」って何のことかしら? 令3条使用人は建設業の営業所の「支店長」や「営業所長」を指す言葉になります あら、そうなの、じゃあ詳しく教えてくださらない? 今回は令3条使用人について、要件などについて詳しく解説していきます。... -

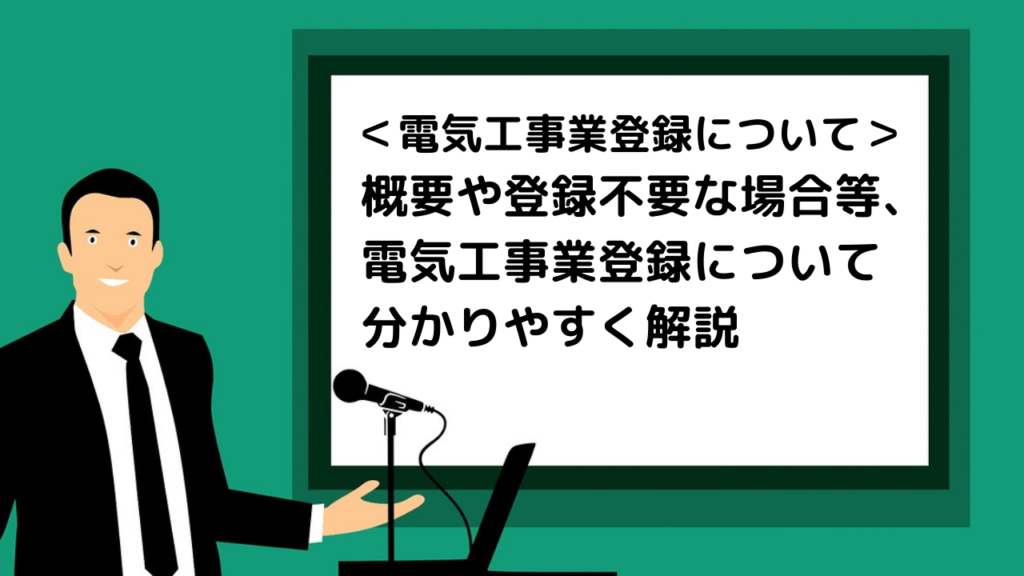
電気工事業登録について、概要や登録不要な場合等について解説
電気工事業の登録って、あまり聞いたことがないのですが、どんな場合に必要なんですか? 今回は電気工事業登録について、概要や登録不要な場合など、わかりやすく解説します 電気工事業登録とは 電気工事業を営もうとする方(自家用電気工作物に係る電気工... -

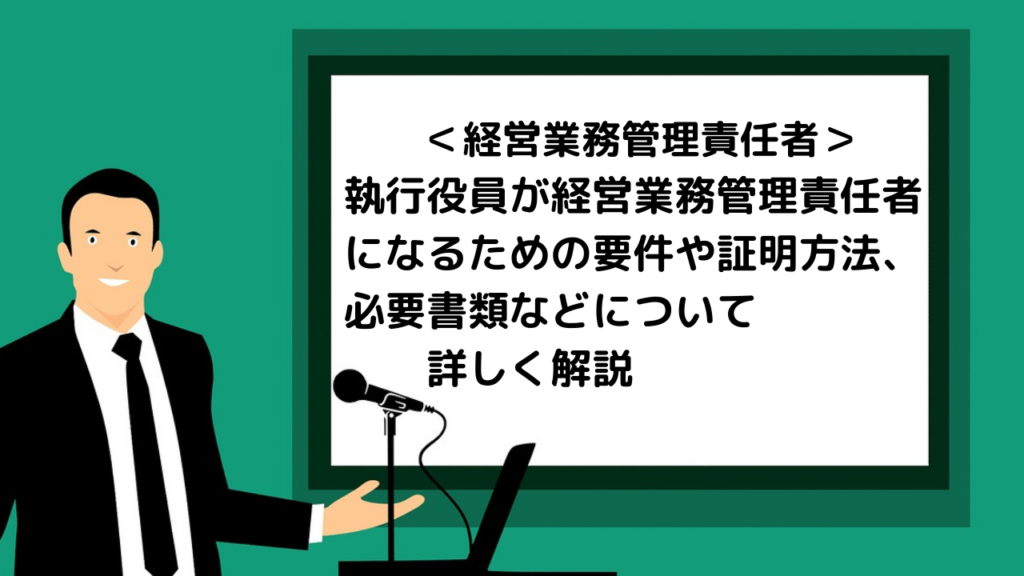
執行役員が経営業務管理責任者になるための要件や証明方法、必要書類などについて詳しく解説
執行役員についても、一定の経験があれば、経営業務管理責任者になることが可能です。ただし、執行役員が経営業務管理責任者になるには、決められた要件があり、必要書類もいろいろと必要になるので、今回は執行役員が経営業務管理責任者になるための条件... -

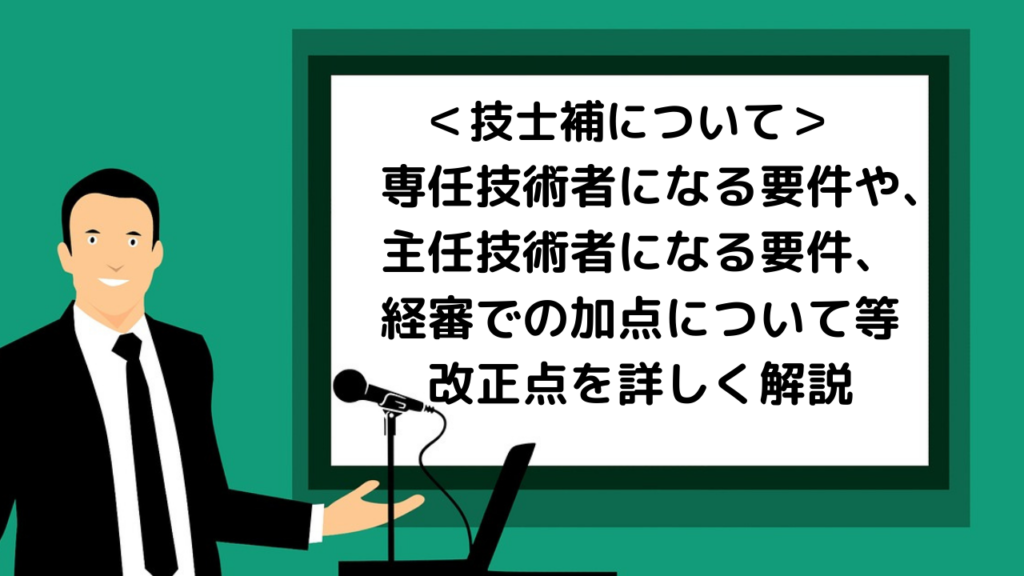
技士補の専任技術者、主任技術者要件や、補佐、経審での加点など詳しく解説
法改正により、技士補が建設業許可の申請や経営事項審査に関わるようになってきましたが、今ひとつわかりにくい部分もあるので今回は技士補について、専任技術者要件や主任技術者要件、経審での加点などをまとめてみました。 尾西先生、技士補の扱いが今一... -

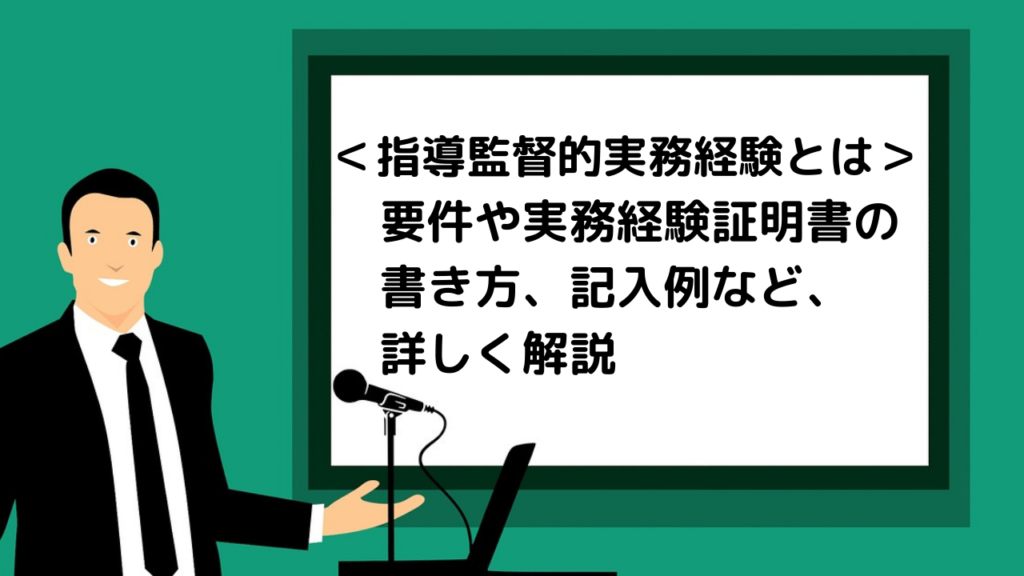
指導監督的実務経験とは、要件や実務経験証明書の書き方など、詳しく解説
特定許可を申請する場合に、指定7業種以外の業種については、「一般の専任技術者要件+指導監督的実務経験」があれば、特定の専任技術者になれるとされています。 お客様から「指導監督的実務経験」について聞かれたのですが、上手く答えれなくて困りまし... -

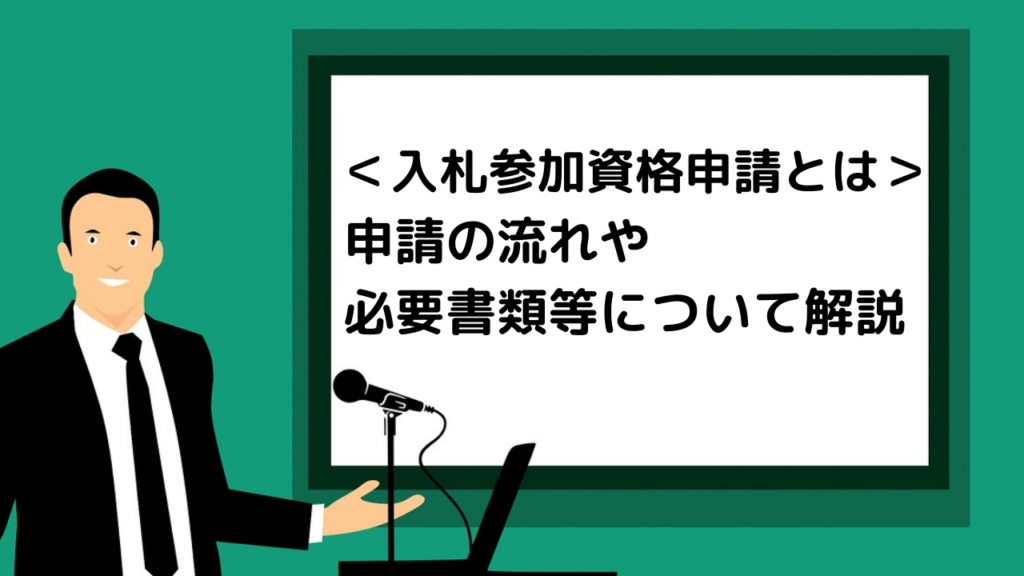
入札参加資格申請とは、申請の流れや必要書類等について解説
入札参加資格申請って公共工事等の入札に参加するのに必要なんですよね? そうです、公共工事の業者の選定は、原則競争入札にて決められることになります では、入札参加資格申請について、詳しく教えてもらえますか?尾西先生 はい、今回は入札参加資格申... -

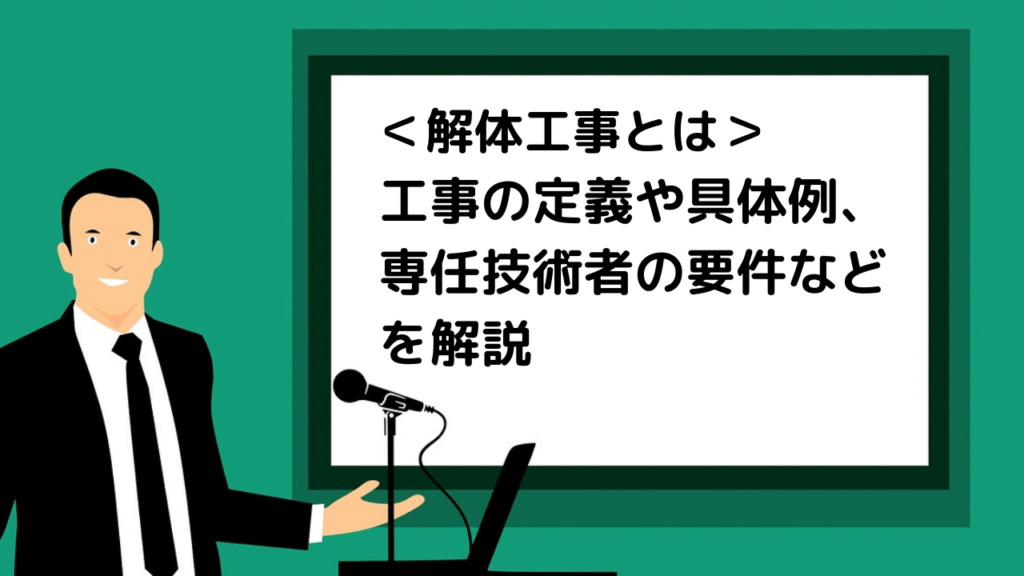
解体工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて解説
建設業許可業種には「解体工事」という業種があります。 当社でも解体工事業の許可を追加したいのだがね 専門工事として、500万円以上の解体工事を請負する場合は、解体工事の許可を追加しないといけませんね では、解体工事の許可について、詳しく教えて... -

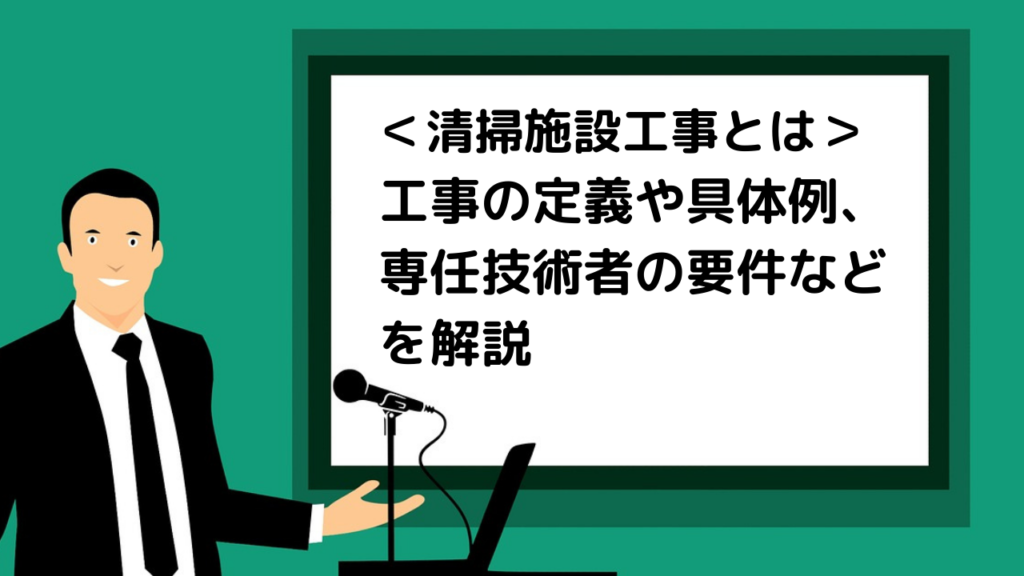
清掃施設工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて解説
建設業許可業種には「清掃施設工事」という業種があります。 清掃施設工事ってどんな工事なんですか? ごみ処理施設などを設置する工事になります なるほど、では清掃施設工事について詳しく教えてもらえますか?尾西先生 わかりました、今回は清掃施設工... -

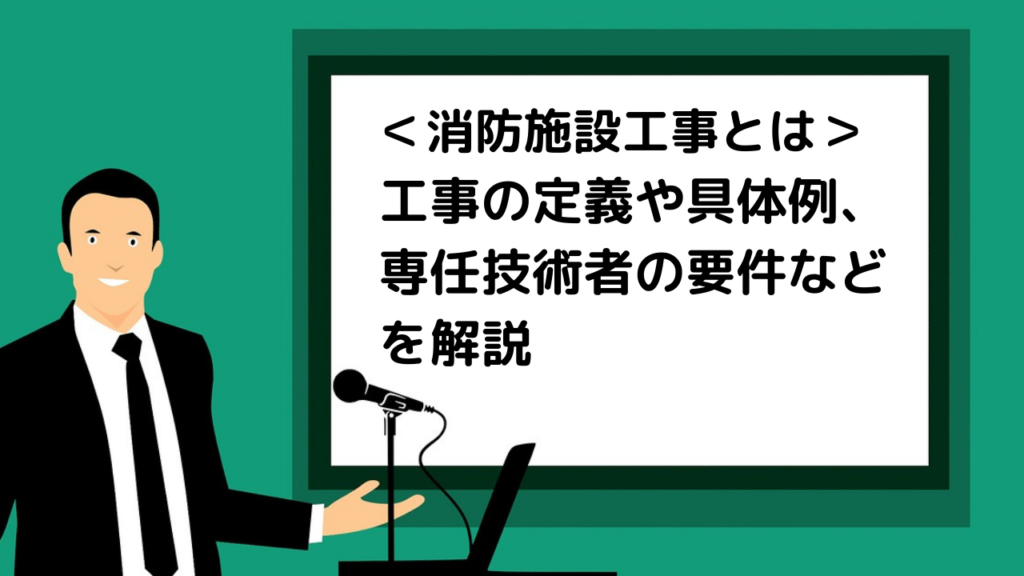
消防施設工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて解説
建設業許可業種には「消防施設工事」という業種があります。 消防施設工事って、消火施設に関する工事のことですか? そうです、他にも火災警報設備の工事や、避難設備の工事などが挙げられます では、消防施設工事について詳しくおしえてもらえますか?尾... -

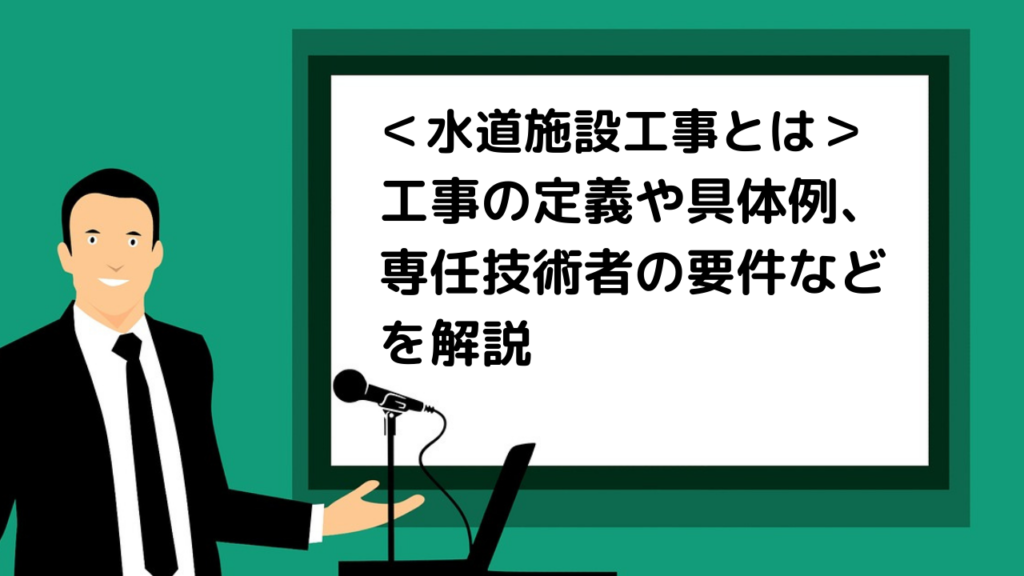
水道施設工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて解説
建設業許可業種には「水道施設工事」という業種があります。 水道施設工事って水道の配管工事とかですか? 上水道の配管設置などは、「管工事」に該当すると思います なるほど、では水道施設工事について、詳しく教えてもらえますか? はい、今回は水道施...